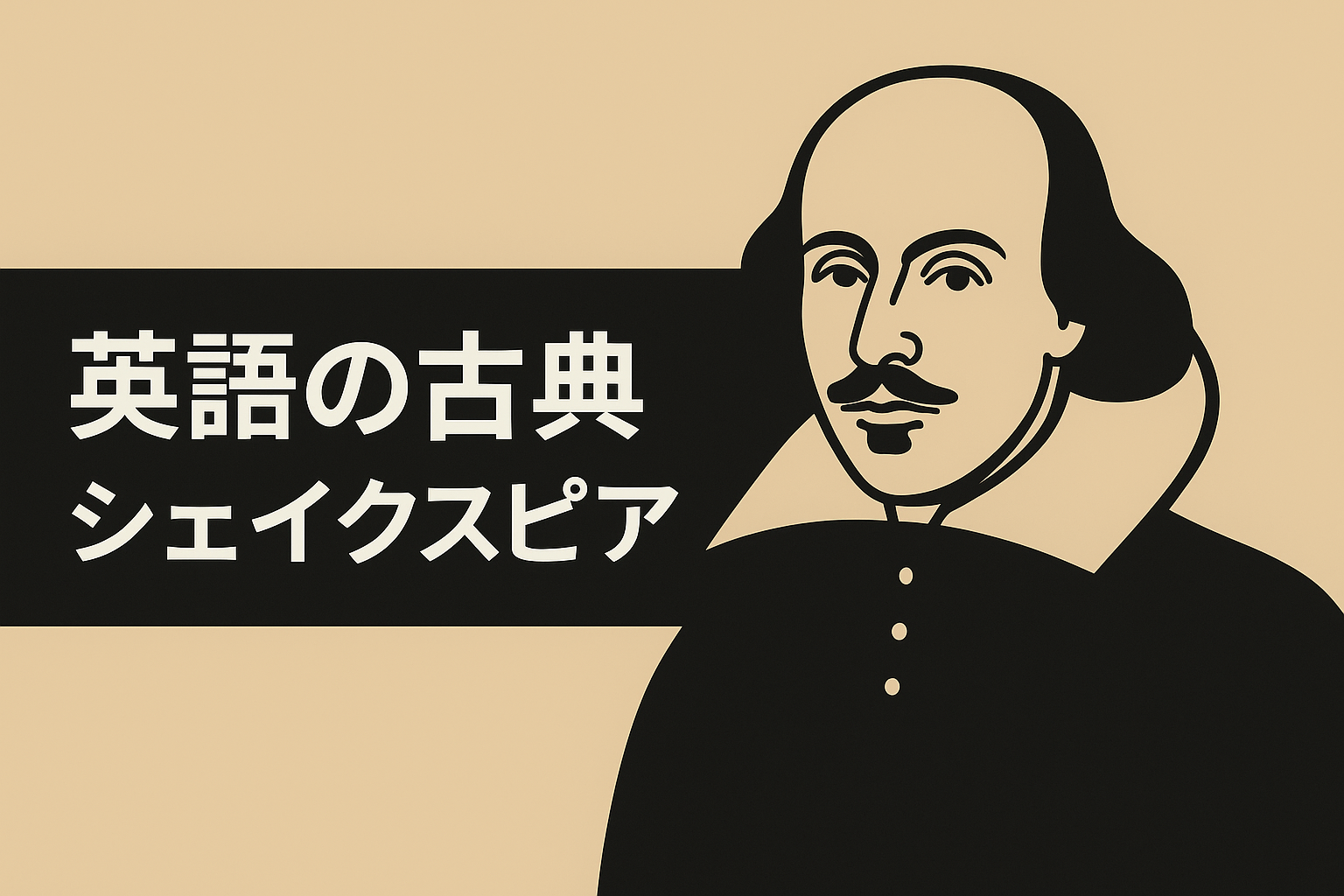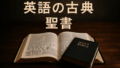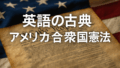イングランドの劇作家・詩人ウィリアム・シェイクスピア(William Shakespeare:1564–1616)の作品は、400年以上経った今も世界中で読まれ、演じられ続けています。彼の戯曲は大きく「喜劇・悲劇・歴史劇・ロマンス劇」に分けられ、さらに年代によって作風の変化が見られます。ここでは、シェイクスピアの創作を初期から晩年まで時代ごとに追い、代表作を紹介していきます。
初期(1590年頃 – 1594年頃)
この時期は劇作家としての登場期で、歴史劇やストレートな喜劇が多く書かれました。台詞は比較的平易で、劇場での娯楽要素が強いのが特徴です。
喜劇
- 『間違いの喜劇』 (The Comedy of Errors)
- 『恋の骨折り損』 (Love’s Labour’s Lost)
- 『二人のヴェローナ人』 (The Two Gentlemen of Verona)
歴史劇
- 『ヘンリー六世』三部作 (Henry VI, Parts 1–3)
- 『リチャード三世』 (Richard III)
悲劇
- 『タイタス・アンドロニカス』 (Titus Andronicus)
- 『ロミオとジュリエット』 (Romeo and Juliet)
有名な一節(『ロミオとジュリエット』第二幕第二場)
原文: “Romeo, Romeo! wherefore art thou Romeo?”
現代英語訳: “Romeo, why are you Romeo?”
→ 「どうしてあなたはロミオなの?」という嘆き。恋愛劇の代名詞とも言える台詞です。
中期(1595年頃 – 1600年頃)
劇作家として円熟し、喜劇と歴史劇に加えて社会性を持つ悲劇も現れ始めます。言葉遊びや比喩が増え、表現はより複雑に。
喜劇
- 『夏の夜の夢』 (A Midsummer Night’s Dream)
- 『ヴェニスの商人』 (The Merchant of Venice)
- 『から騒ぎ』 (Much Ado About Nothing)
- 『お気に召すまま』 (As You Like It)
歴史劇
- 『リチャード二世』 (Richard II)
- 『ヘンリー四世』二部作 (Henry IV, Parts 1–2)
- 『ヘンリー五世』 (Henry V)
悲劇
- 『ジュリアス・シーザー』 (Julius Caesar)
有名な一節(『ジュリアス・シーザー』第三幕第一場)
原文: “Et tu, Brute?”
現代英語訳: “And you too, Brutus?”
→ 「ブルータス、お前もか!」という有名な台詞。裏切りと友情の複雑さを象徴しています。
後期(1601年頃 – 1608年頃)
この時期は「四大悲劇」が書かれ、シェイクスピアの頂点とされる時代です。人間の内面や権力、欲望を深く描き、文学史に残る名作が集中しました。
四大悲劇
- 『ハムレット』 (Hamlet)
- 『オセロー』 (Othello)
- 『リア王』 (King Lear)
- 『マクベス』 (Macbeth)
悲喜劇・問題劇
- 『尺には尺を』 (Measure for Measure)
- 『トロイラスとクレシダ』 (Troilus and Cressida)
- 『終わりよければすべてよし』 (All’s Well That Ends Well)
有名な一節(『ハムレット』第三幕第一場)
原文: “To be, or not to be: that is the question.”
現代英語訳: “To live, or not to live: that is the question.”
→ 「生きるべきか、死ぬべきか、それが問題だ」。人生と存在の意味を問う、最も有名な台詞のひとつです。
晩期(1609年頃 – 1613年頃)
晩年は「ロマンス劇」と呼ばれる和解・調和をテーマにした作品群が特徴。悲劇的要素は薄れ、幻想的で穏やかな作風になります。
ロマンス劇
- 『冬物語』 (The Winter’s Tale)
- 『テンペスト』 (The Tempest)
歴史劇
- 『ヘンリー八世』 (Henry VIII)
有名な一節(『テンペスト』第四幕第一場)
原文: “We are such stuff as dreams are made on.”
現代英語訳: “We are made of the same stuff as dreams.”
→ 「私たちは夢でできている」。人生のはかなさと幻想的な雰囲気を象徴する台詞です。
シェイクスピアの学習教材
シェイクスピアの英語は「初期近代英語(Early Modern English)」であり、現代の英語学習者には難解です。現代英語とは異なる語彙や文法、独特な言い回しが多く、いきなり読むのは非常にハードルが高いです。ですので、現代語訳を併用して、ストーリーや登場人物の感情をスムーズに理解できるようにすると、挫折せずに楽しく作品を読み進めることができるかと思います。
ストーリーを理解したい初心者向け
『No Fear Shakespeare』シリーズ
- 教育系ウェブサイト「SparkNotes」が提供しているシリーズです。
公式サイトはこちら:https://www.sparknotes.com/shakespeare/ - 特徴: 「恐怖なし」という名前の通り、初めてシェイクスピアに触れる人向けに作られたシリーズです。左ページに原文、右ページに現代英語訳が対照的に掲載されているのが特徴です。
- おすすめポイント
- 原文と現代語訳をすぐに比較できる: 辞書を引く手間が省け、読解のストレスが少ないです。
- ストーリーに集中できる: 難しい単語や表現に悩まず、物語の流れをスムーズに把握できます。
- 音声版も利用可能: 公式サイトから無料で音声版を聴くことができ、リスニングの練習にもなります。
原文読解の力をつけたい中級者向け
『The Folger Shakespeare Library』シリーズ
- アメリカにある研究図書館「Folger Shakespeare Library」が運営しています。
公式サイトはこちら:https://www.folger.edu/explore/shakespeares-works/
- 特徴: 原文をメインに据え、各ページの下部に難しい単語の注釈や現代語訳が簡潔にまとめられています。「原文に挑戦し、分からない部分だけ注釈で確認する」という学習スタイルに適しています。
- おすすめポイント
- 原文を読む練習になる: 本文は原文のみなので、自力で読む力が養えます。
- 文学的な背景も学べる: 注釈には単語の意味だけでなく、当時の文化や歴史的な背景に関する解説も含まれています。
『No Fear Shakespeare』で物語の全体像をつかんでから、『The Folger Shakespeare Library』でより深く作品を掘り下げていく、といったステップアップがよいかと思います。
まとめ
シェイクスピアの作品は、初期の歴史劇や喜劇から始まり、中期の円熟した喜劇と悲劇、後期の四大悲劇、そして晩年のロマンス劇へと移り変わりました。各時代ごとの代表作を追うことで、シェイクスピアの文学的成長とともに、英語表現の奥深さに触れることができます。
学習者にとっては、まず現代英語訳を足掛かりにしてから、名台詞を原文に進むと、シェイクスピアの世界を身近に感じやすくなるかと思います。