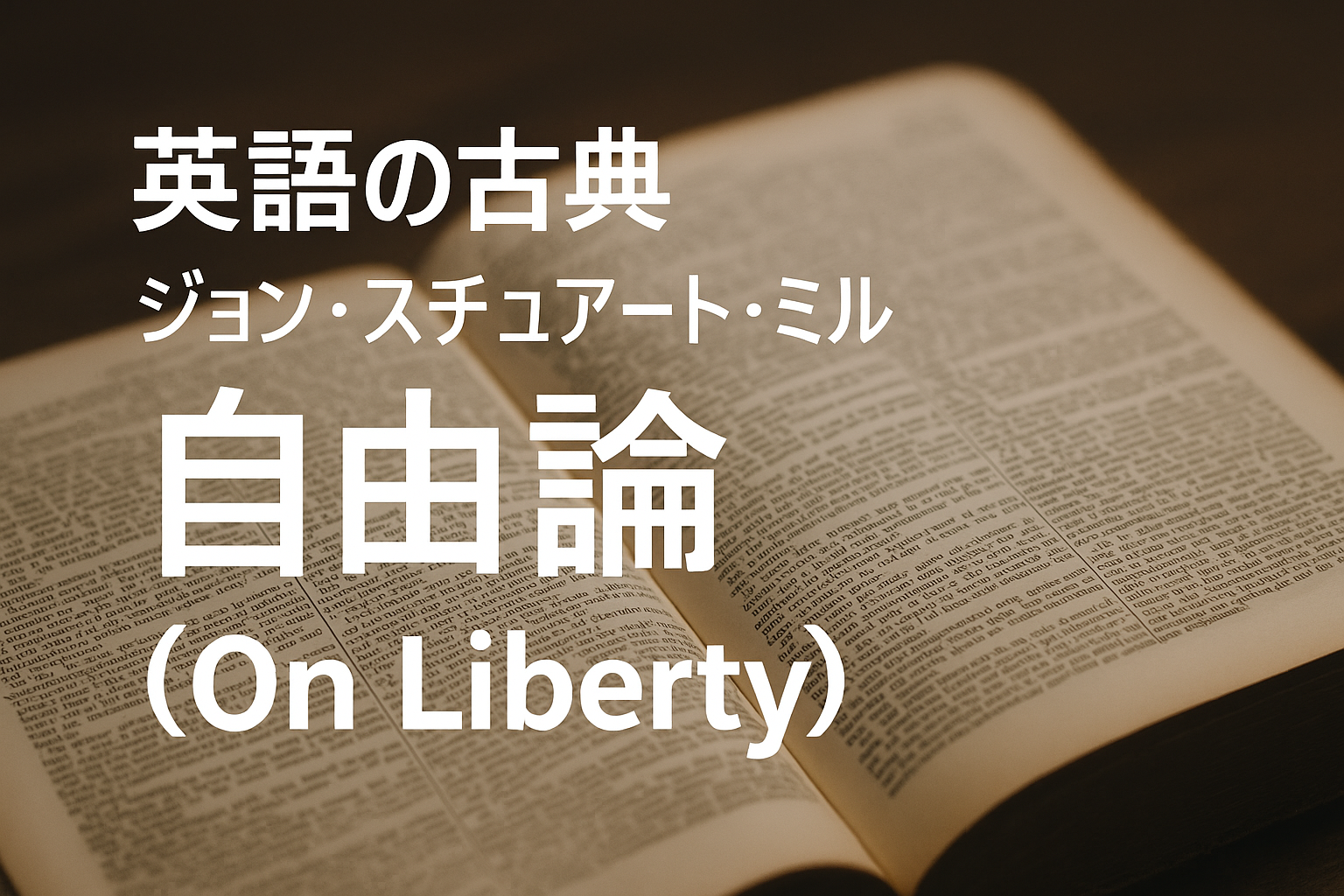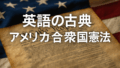イギリスの哲学者、経済学者であったジョン・スチュアート・ミル(John Stuart Mill, 1806–1873)の『自由論』も、英語の古典として重視されているものの一つです。彼は近代自由主義の中心的人物として知られています。
ジョン・スチュアート・ミルとは
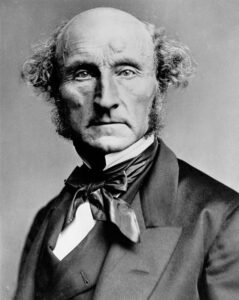
John Stuart Mill
ミルは父ジェームズ・ミルのもとで幼少期から厳しい教育を受け、わずか10代で古典ギリシア語やラテン語を学び、論理学や政治経済を習得していたといいます。父とともに当時の思想家ジェレミー・ベンサムの功利主義(Utilitarianism) を受け継ぎつつ、「より人間的で温かい思想」に発展させた人物であるとされます。
ミルは公務員としてイースト・インディア会社に勤めながら、多くの著作を通して「個人」「社会」「幸福」について考え続け、代表作『功利主義論(Utilitarianism)』『女性の解放(The Subjection of Women)』、そして本稿で取り上げる『自由論(On Liberty)』は、その思想の核となっています。
功利主義(Utilitarianism)とは何か
ミルの思想を理解する上で欠かせないのが、功利主義(Utilitarianism) という考え方です。これは、「行為の善悪は、それがどれだけ多くの人に幸福をもたらすかによって決まる」という倫理学の立場です。
功利主義を体系化したのは、ミルの師である ジェレミー・ベンサム(Jeremy Bentham, 1748–1832) でした。ベンサムは人間の行動を「快楽」と「苦痛」の尺度で測り、社会全体の幸福量を最大化することを目指しました。彼にとって「幸福」は計量可能なものであり、量的な快楽を重視していたのが特徴です。
しかしミルは、その考え方を受け継ぎながらも重要な修正を加えました。彼は「すべての快楽が同じ価値を持つわけではない」と考え、質的な違いを重視しました。
“It is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied.”
(満足した豚であるよりも、不満足な人間であるほうがよい。)
この一文に、ミルの人間観が表れていると思われます。知性や道徳、感情の深さといった「高次の快楽」は、単なる物質的な満足とは比べものにならないという人間的価値への信頼が、ミルの功利主義の核でした。
ベンサムが「幸福の量」を問題にしたのに対し、ミルは「幸福の質」と「個人の尊厳」に焦点を当てました。この違いが、『自由論』を支える哲学的背景を形づくっています。
功利主義というと冷たい合理主義のように聞こえる面もありますが、ミルの思想を読むと、人間らしい温かさと理性が共存していることがわかります。
ミルが展開した思想
ミルの思想の中心には、個人の自由を最大限に尊重する社会という理想があります。ただし彼の言う「自由」とは、好き勝手に行動することではありません。
他者を傷つけない限りにおいて、自分自身の人生を自由に選ぶという考え方は、のちに「他者危害原則(The Harm Principle)」として知られるようになりました。
“The only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community, against his will, is to prevent harm to others.”
(文明社会において、個人の意志に反して権力を行使できる唯一の正当な理由は、他者への害を防ぐことである。)
この一文に、ミルが描いた「自由」のすべてが凝縮されているように思います。個人の行動は基本的に自由であるべきだが、その自由の限界は他人の権利との境界にあるという考えは、現代の民主社会にも深く影響を与えているといわれています。
もうひとつ印象的なのは、ミルが「世論」という見えない圧力にも注意を促している点です。社会が「正しい」と信じる価値観が、時に人々の個性や思想を押しつぶしてしまう「多数派の専制(the tyranny of the majority)」という問題意識は、SNSなどで「同調圧力」を感じる現代にも通じる部分があるように思います。
『自由論(On Liberty)』の内容と意義
『自由論』は1859年に出版されました。この作品は「個人の自由と社会の統制」をテーマにした近代自由主義の古典であり、今でも多くの国で政治哲学の教科書に取り上げられています。
主な章構成は以下のようになっています。
| 章 | 内容概要 |
|---|---|
| 第1章 | 自由の意味と必要性 ― 個人の自由を制限する危険性 |
| 第2章 | 思想と言論の自由 ― 真理は自由な討論から生まれる |
| 第3章 | 個性と自立 ― 他人に合わせず自分らしく生きる意義 |
| 第4章 | 社会の権威と個人の自由 ― 社会的圧力がもたらす危険 |
| 第5章 | 自由の原則の適用 ― 現実社会への具体的な提言 |
全体を通してミルは、「自由とは理性による自己統制である」と考えています。特に第三章の「個性(Individuality)」の部分は印象的で、人が他人と違う意見や生き方を持つことの大切さを情熱的に語っています。
“Over himself, over his own body and mind, the individual is sovereign.”
(人は自分自身の身体と心において、主権者である。)
この文を読むと、「liberty」という言葉が単なる自由ではなく、「自己決定」「責任」「尊厳」といった重みを持っていることに気づかされるかと思います。
同時代の背景と思想形成の流れ
『自由論』が書かれた19世紀半ばのイギリスは、ヴィクトリア朝時代の真っ只中でした。
産業革命によって都市が急速に発展し、人々の生活は豊かになりつつも、格差や労働問題が社会の不安を広げていました。道徳的には保守的で、「男性中心の社会秩序」や「道徳的規範の厳格さ」が重んじられていた時代とされます。

Harriet Taylor
ミルはそうした風潮の中で、「自由とは何か」「社会が個人にどこまで介入できるのか」を問いました。そして、その思想の形成に大きな影響を与えたのが、ハリエット・テイラー(Harriet Taylor) という女性でした。彼女はミルの長年の友人であり、のちに妻となります。
ハリエットは、女性の教育と社会的平等を訴えた先進的な思想家でした。二人の対話を通じて、ミルは「自由」と「平等」は切り離せないという考えに至ります。実際、『自由論』にはハリエットへの献辞があり、その内容はほぼ共著に近いとされています。
人間の尊厳を守る哲学が、個人的な愛情や尊敬から生まれたという点も、ミルの思想の温かさを感じさせます。
日本への影響
ミルの『自由論』は日本にも早くから紹介されました。1872年(明治5年)に中村正直(なかむら まさなお)が刊行した『自由之理(じゆうのことわり)』 にが初の邦訳です。この翻訳を通じて、ミルの思想は日本の知識人社会に浸透していったと言われています。
明治期の知識人である 福澤諭吉 や 西周(にし あまね) も『自由論』を読み、西洋思想を学ぶ重要な資料として位置づけたとされます。
当時の日本社会は、封建制から近代国家へと移行する過程にあり、「個人の自由」という概念はまだ新しいものでした。ミルの思想は、「近代的な主体としての個人」という考え方を日本に広めるきっかけになったと言われています。
こうした流れを見ると、『自由論』は単なるイギリス思想の産物ではなく、世界的に共有される「自由の哲学」として受け継がれてきたことが分かります。
「自由」の捉え方
『自由論』を読んでいて感じるのは、ミルが描く「自由」が単なる“freedom”ではなく、他者と共に生きる力を意味しているということです。彼にとって自由とは、自分の考えを持ちつつ、他人の考えも尊重することであり、それは「自立」と「共感」を両立させるための思考法でもあるのだと思います。
英語の “liberty” という言葉には、自由と同時に「節度」や「尊厳」のニュアンスも含まれています。この言葉をどう理解するかで、英語そのものの捉え方も変わってくるかと思います。政治的文脈では、言葉の厳密な定義自体が難しく、意味が漂っていて議論され続けている状態こそが大事だという考え方もあります。その議論の内容も時代によって移り変わりますので、ただ意味を覚えるだけでなく、「この言葉がどんな価値観を背負っているのか」を考えることが必要になるかと思います。
英語で読む『On Liberty』
ミルの英語は、19世紀中期の近代英語(Modern English)で、文法や語彙は現代とそこまで大きな違いはありません。
文章は長めですが、節ごとの流れが明確で、英語の構造をつかむ練習に向いているかと思います。また、同じ語句を繰り返すことで議論を強調する文体は、リーディング力を高める訓練にもなるとも言われています。
英語版を読む際には、以下のリソースが便利です。
Project Gutenberg(無料原文)
https://www.gutenberg.org/ebooks/34901
LibriVox(無料朗読版)
https://librivox.org/on-liberty-by-john-stuart-mill/
Modern English paraphrase(現代英語訳)
“A Translation to Modern English” などのタイトルでKindleで無料または安価で収録。
原文を読むのが難しいときは、対訳や現代英語版を併読するのがよいと思います。また、朗読音声を聴くと、文体のリズムや抑揚がよく分かり、英語の響きを感じることができます。
日本語訳
現在出版されている入手可能なの邦訳は以下のとおりです。
| 訳者 | 書籍名 | 出版社 | 発行年 | 備考 |
| 山岡洋一 | 『自由論』 | 日経BPクラシックス | 2006年 | 元は光文社古典新訳文庫で刊行。現代的な訳で読みやすいとされます。 |
| 斉藤悦則 | 『自由論』 | 光文社古典新訳文庫 | 2012年 | 山岡訳に代わる形で刊行された新訳です。 |
| 関口正司 | 『自由論』 | 岩波文庫 | 2020年 | 岩波文庫の最新訳です。 |
| 芝瑞紀 | 『すらすら読める新訳 自由論』 | サンマーク出版 | 2024年 | 最も新しい訳です。 |
まとめ
ジョン・スチュアート・ミルの『自由論』は、150年以上前に書かれたものですが、「他者と共に生きる中で、自分の自由をどう守るか」という、現代の私たちにも通じる普遍的なテーマかと思います。
英語で書かれた思想書としての『On Liberty』は、言葉のリズム、論理の展開、英語が持つ理性の力を感じられる一冊だと思います。読んでみると、「英語を学ぶこと」と「自由を考えること」が、実はとても近いところにあるようにも思えてきます。
参考文献
- 関口正司 『J・S・ミル-自由を探究した思想家』 中公新書 2023年
- 児玉聡 『哲学古典授業 ミル『自由論』の歩き方』 光文社新書 2024年
- 薬袋善郎 『ミル『自由論』 原書精読への序説』 研究社 2020年
- 薬袋善郎 『ミル『自由論』原書精読2: 行動制限の原理』 研究社 2024年