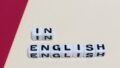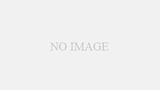日本の英語教育の問題点とは
日本の英語教育では、中学・高校の6年間にわたり英語を学ぶにもかかわらず、教科書や副読本(サイドリーダー)、さらには受験勉強を含めても、実際に触れる英語の量は決して多いとはいえません。
そのため、単語や文法の知識をある程度身につけたとしても、実際に英語を使って自由に読んだり話したりする場面では、多くの学習者が壁を感じてしまいます。これは、英語学習が「試験のための知識」としての側面に偏りすぎていることも一因です。知識としては習得しているのに、それを実践で使う訓練がほとんど行われていないのです。
また、日本における英語のリーディング指導では、英文を一語一句日本語に訳すというプロセスが長らく重視されてきました。多くの場合、辞書を手元に置き、わからない単語や熟語の意味を調べ、文型や構文を確認しながら、ゆっくり丁寧に読み進めていくというスタイルです。確かにこの方法は、英語の構造や語彙を深く理解するうえでは有効ですが、読解にかかる時間が長く、実践的な読解力が養われにくいという課題も抱えています。
英語に触れる絶対的な量が少ないうえに、このような精密な読み方を続けていては、実際に“使える”英語力を身につけることは難しいと言えます。むしろ、「英文を読む=日本語に訳す」という固定観念が強くなりすぎてしまい、英語をそのまま英語で理解するという感覚を育てる妨げにもなっているのではないでしょうか。
概要をつかむ読み方を意識する
もちろん、一語一句を丁寧に読み取る精読は、専門的な内容を理解したり、他者の意見を分析したりする場面では有効です。しかし、私たちは日本語でも新聞や雑誌を読むときには、すべてを精読するのではなく、必要な情報をざっと拾い読みして全体の内容をつかもうとしています。英語でも同じように、文の構成や論理の流れを追うといった「概要把握型」の読み方が、実用的な場面では必要とされます。
このようなスキミング(ざっと読む)やスキャニング(必要な情報だけを探す)といった読解スタイルは、特にビジネスシーンや海外旅行、留学先での情報収集など、時間に制約がある中で活用されます。限られた時間の中で大量の情報を処理するには、細部にとらわれずに文脈全体を把握する力が求められます。
その際に意識すべきポイントは、「筆者がどのような情報や意見、感情を伝えようとしているのか」を読み取ろうとすることです。一語一句にとらわれていては、筆者の意図や文章全体の流れに意識が向きにくくなってしまいます。語句の意味に固執するよりも、文と文、段落と段落のつながりを意識することで、文章全体の「流れ」を捉えることができるようになります。
英文を読むときには、各段落ごとにポイントを押さえながら、トピックがどう展開されているかをテンポよく読み進めてみましょう。わからない単語があっても、毎回立ち止まらず、文脈から意味を想像してみるようにします。実際には、すべての単語の意味がわからなくても、既に知っている語彙だけで内容の大まかな理解が可能なことも多いからです。
こうした「軽やかな読み方」で多読の経験を積んでいくことが、英語に対する直感的な理解力、いわゆる“英語勘”を養ううえでも非常に効果的です。多読によって英語のリズムや語彙の感覚が自然と身についていき、やがて「英語を英語のまま理解する力」が育っていきます。
さらに、読解力の向上はスピーキングやライティングといったアウトプット能力にも良い影響を与えるため、英語力全体の底上げにもつながります。読解スタイルの見直しと多読の習慣化を通じて、より実用的な英語力を身につけていきましょう。